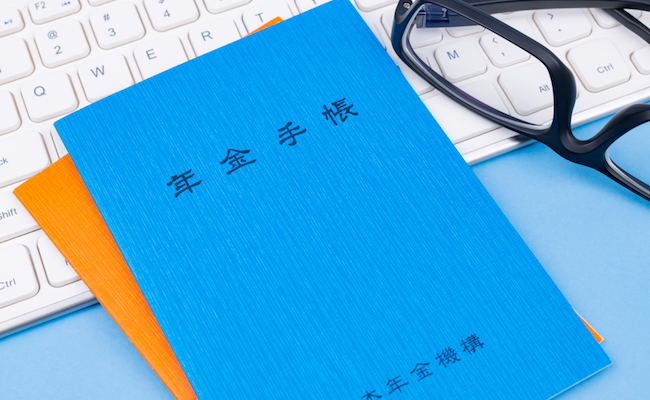2019年11月29日に101歳で亡くなった中曽根康弘元総理。1982年に内閣総理大臣に就任すると、様々な改革に着手。首相在職日数1806日の中で、多くの功績を残しました。国鉄や電電公社、専売公社の民営化がまず挙げられると思いますが、実は年金についても中曽根元総理は大きな改正を成し遂げていました。そんな中曽根元総理の年金改正について、著者のhirokiさんが無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の中で詳しく紹介。何かと話題になる年金についての歴史や変遷について教えてくれます。
中曽根元総理の大きな功績!昭和60年年金大改正での基礎年金導入
中曽根康弘元総理が101歳で亡くなられましたよね。凄い長生き!
中曽根さんは昭和57年11月27日から昭和62年11月6日まで首相を務めた人ですが、年金の大改革の時の大変な功労者でもあります。中曽根さんが年金?って疑問に思われた方も多いかもしれないですね^^;
中曽根総理を思い出す時、国鉄(JR)、電電公社(NTT)、日本たばこ産業(JT)の国営だった企業を民営化したというイメージが強いですよね。年金ではよくこれらを三共済と呼んでます(平成9年4月に厚生年金に統合された企業)。特に国鉄共済組合は赤字だらけでほとんど破綻寸前だったから、あの時は国家公務員共済や厚生年金からの高額な支援金、そして国鉄自身の大幅な人員整理で何とか経営を立て直した。
国鉄が危機的状況に陥ったのは、戦前戦後に輸送力の増強や海外引揚者(旧満州とか外国に住んでた日本人が日本に帰ってきた)の雇用のために国策に従って大量に雇用した職員が昭和40年代ごろから一斉に退職していったため。さらに、昭和50年代からの自動車産業の発展により、鉄道産業が縮小されてしまい、昭和30年ごろには50万人ほどいた職員が30万人まで縮小された(平成2年には約20万人まで縮小)。縮小した職員で退職した職員を支える状態になってしまった。
しかし中曽根内閣の最大の目玉はなんといっても昭和60年の年金大改正である「基礎年金導入」でありました。よく学校とかに使われてる歴史の教科書とかはさっきの国鉄とかの三公社の民営化あたりが主に書いてると思いますが、中曽根行政改革の最大の目玉は年金改革による基礎年金の導入と、健康保険に本人一割負担を医療保険改革でした。当時の社会保障分野の行政改革こそ中曽根内閣の最大の改革だった。この時に年金の形が大きく変貌しました。
国民年金の始まった当初の昭和36年4月は元々は国民年金は自営業者とか零細企業の年金制度でした。自ら定額の国民年金保険料を支払って、自ら備える。でも産業の変化(農業などの自営業から、急激に会社に雇用される人が増えていった)から、国民年金保険料を支払う人がそもそも減少していった(国民年金→厚生年金への流入)。このため、国民年金の財政は産業の変化で被保険者が少なくなっていき、赤字になっていきました。
そんな危機的状況にあった国民年金を、昭和60年改正でどんな業種だろうが加入させるという基礎年金制度に変えたんです。どんな業種(自営業、サラリーマン、公務員)であれ、20歳から60歳までの全員が国民年金(給付は基礎年金)に加入し、その国民年金の財源はみんなの業種に関係なく、公平に保険料を負担しあい、公平に国民年金から老齢基礎年金を支給しようという事になったのであります。
みんなの共通部分の基礎的な給付は国民年金から支払い、その上に過去の給与に比例して年金額が変化する厚生年金や共済を支給しようと。今もこの形が、年金の形となっています。中曽根内閣の頃にこの年金の大手術ともいえる改正がなされました。
このようにして国民年金は業種が変わっても影響を受けないものとなり(転職しようが国民年金の被保険者になるから)、財政が安定するようになったのであります。